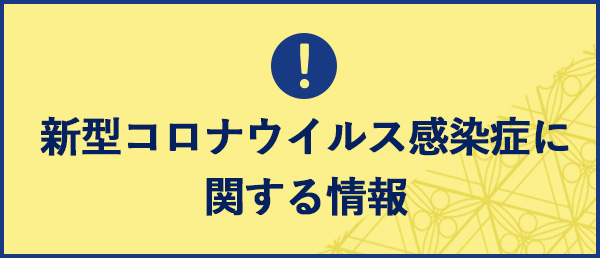ホーム > 県政情報 > 知事室 > 県議会での知事説明 > 県議会知事説明要旨2025年 > 2月定例会(令和7年2月19日)
更新日:2025年2月19日
ここから本文です。
2月定例会(令和7年2月19日)
令和7年県議会2月定例会の開会に当たり、一言申し上げます。
県政運営5期目に当たって
私は、このたびの選挙を通して、「県民の皆様とともに常にチャレンジを続けながら、山形の未来を創っていきたい。」という想いや、本県の将来ビジョン、重要施策について県民の皆様にお伝えしながら、県政に対する幅広い御意見にも耳を傾けてまいりました。
県民お一人おひとりが未来に明るい展望を抱き、暮らし続けたいと思えるような山形県をつくっていくことが私の使命であると、改めて、強く感じたところです。
5期目に当たりましては、知事就任以来、一貫して掲げてまいりました「心の通う温かい県政」の基本姿勢のもと、「県民視点」、「対話重視」、「現場主義」を改めて徹底するとともに、市町村をはじめ、多様な主体との連携を一層強化することにより、施策の実効性を高め、県全体にその効果を波及させてまいりたいと考えております。
これからの4年間、県民の皆様との「共創」を大切にしながら、県民の皆様の幸せのため、県土発展のため、そして山形県の明るい未来のために、全身全霊を尽くしてまいります。
本県を取り巻く情勢
次に、令和6年7月25日からの大雨による災害の復旧・復興について申し上げます。
選挙期間中、被災地を含め県内各地を訪問しましたが、多くの方々から「復旧・復興に向けて、頑張ってほしい。」との声を頂戴しました。仮設住宅にお住まいの方など、被害に遭われた方々とも直接お会いし、また、厳冬の被災地の光景を目の当たりにして、「全力で復旧・復興を成し遂げなければならない。」との決意を新たにしたところであります。
一日も早く日常生活を取り戻すことができるよう、被災地の復旧・復興に向けて、市町村や関係者の皆様と連携し、被災者お一人おひとりに寄り添いながら、全力を挙げて取り組んでまいります。
次に、今冬の大雪の状況等について申し上げます。
今冬の大雪により、雪下ろしや除雪作業中の事故が相次いでおり、人的被害は、2月17日現在、死者3名、負傷者93名の合計96名となっております。亡くなられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、怪我を負われた方々の一日も早い回復を願っております。
県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、2月5日から大雪となり、県内の広範囲にわたって平年を上回る積雪となりました。
そのため、県では、2月8日に山形県豪雪災害対策本部を設置し、雪害事故防止の注意喚起などについて、市町村や関係機関と連携して対応を進めてきたところです。
農林水産関係につきましても被害が発生していることから、被害防止に向けた技術対策の徹底を呼びかけるとともに、2月12日には大雪に係る農林水産関係相談窓口を設置したところです。
また、私自身も、農業被害現場を訪問し、地元自治体や被害に遭われた方々から、果樹の枝折れやビニールハウス損壊の被害状況などについて、直接お話をお聞きしてまいりました。そのうえで、県単独災害対策事業などによる支援策を2月14日に発動いたしました。
今後も、冬型の気圧配置がしばらく続きますので、さらなる積雪による被害、その後は気温の上昇に伴い、落雪による事故や雪崩による被害も懸念されますので、引き続き市町村とともに県民の皆様への注意喚起を行いながら、雪対策に万全を期してまいります。
次に、遊佐町沖の洋上風力発電事業者の選定について申し上げます。
遊佐町沖で取組みが進む洋上風力発電事業につきまして、去る12月24日、経済産業省及び国土交通省から、事業者として「山形遊佐洋上風力合同会社」を選定したとの発表がありました。このたびの選定を受けて、本県遊佐町沖でいよいよ本格的に事業が始動いたします。
政府は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化の切り札として位置付けており、遊佐町沖事業の推進は、「山形県エネルギー戦略」に掲げる大規模再エネ電源の開発に大きく寄与することはもとより、漁業の持続的な成長や地域産業の振興、若者の働く場の創出など、遊佐町、ひいては本県の発展につながるものと考えております。
県としましては、政府や遊佐町、地域の関係者の皆様、選定された事業者と連携し、地域協調型の洋上風力発電の実現を通して地域の活性化に資するよう引き続き取り組んでまいります。
それでは、提案いたしました議案の説明に先立ち、県政運営の所信の一端を申し上げ、議員各位並びに県民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
これからの県づくりの基本的考え方
本年1月1日現在の本県人口は、100万7千人余りとなっており、本年中に100万人を割ることが見込まれております。
私は、知事就任以来、人口減少問題を県政の最重要課題として、その対策に力を入れて取り組んでまいりました。しかしながら、全国的な傾向ではありますが、婚姻率・出生率の低下が続き、進学・就職等を契機とした若年層の県外流出も相まって、少子高齢化を伴う人口減少には歯止めがかかっておりません。
海外に目を向けますと、米国の新政権発足に伴い諸政策の見直し等の動きが見られるほか、世界各地で紛争や政情不安などの不安定な国際情勢が続き、物価・エネルギー価格は高止まりしています。加えて、気候変動が加速し、世界的に風水害や酷暑、山林火災などが深刻化しています。
一方で、ロボットや人工知能、仮想空間などの技術革新は、産業構造や人々の生活スタイルに大きな変革をもたらしています。世界の不確実性が高まる中、激しい変化に身をすくめ、荒波が過ぎるのを待つのではなく、ピンチをいかにチャンスに変えていくかという、しなやかな発想と知恵が問われていると思います。
石破内閣は、「地方創生2.0」を掲げ、「東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散」や、「若者や女性にも選ばれる地方の構築」に向けた政策の強化などを打ち出しています。こうした政府の動きとも連動しながら、本県での暮らしの魅力を高め、誰もが住みやすく、幸せを感じることができる山形県をつくっていくことが何よりも重要であります。
本県には、豊かな自然や先人から受け継がれてきた優れた文化、人と人との絆の強さ、ものづくりや農の匠の技など、多くの魅力や資源があります。また、本県の歴史・文化の根底には、人と自然との望ましい関わり合い、日々の暮らしや地域における支え合い、お互いを活かし合う精神といった「共生」の考え方、さらには、地域の企業や大学など多様な主体が力を合わせ、新たな価値を創造してきた「共創」の考え方があります。
世界に誇れる山形の力を信じ、先人たちが積み上げてきた価値をしっかりと引き継ぎながら、新たな創意工夫にも積極的に挑戦することで、持続的に発展していくことができる山形県をつくっていきたいと考えております。
そのため、次の5つのチャレンジを掲げ、世界に誇れる山形ならではの「幸せな育ち、幸せな暮らし」の実現を目指してまいります。
1つ目は、「県民が幸せを実感できる山形県」であります。
政府の統計データなど、客観的な指標の分析に基づく最新の「幸福度ランキング」において、本県の幸福度は47都道府県中8位となっており、高い水準を維持してきていますが、一方で、若年層、特に女性の県外流出が続いております。この最大の要因は「仕事・賃金」であり、若者・女性を惹きつける地域づくりを進めるため、経済界と一緒になって、その志向に合った職場づくりや魅力ある働く場の創出・拡大に取り組んでまいります。
子育て・教育環境の充実も重要であります。「こどもまんなか山形」を推進し、子育てに要する経済的負担の軽減や子育てと仕事の両立支援に、引き続き、力を入れてまいります。また、ICTを活用した学びや国際教育、アントレプレナーシップ教育など、質の高い教育環境の整備を進めてまいります。
併せまして、本県の豊かな自然と環境を守るための取組みや、文化芸術・スポーツ施設の整備・活用等、文化・スポーツの振興を通して、持続可能で、活力あふれる地域づくりを推進してまいります。
2つ目は、「安全安心に暮らせる山形県」であります。
暮らしと経済活動の基盤は、県民の安全安心であります。そのため、まず、頻発・激甚化する災害に対し、ハード・ソフト両面での防災力の強化による県土強靭化を早急に進めていく必要があります。
令和6年7月の大雨災害からの迅速な復旧・復興を進めるとともに、河川整備や流下能力向上等による治水対策を推進してまいります。併せまして、こどもの頃からの防災教育の充実、学校・企業・福祉施設等における備えの強化や女性の視点も活かした災害対応など、地域総ぐるみでの防災力の向上に取り組んでまいります。
県民生活の基盤となる社会資本の整備も前に進めていく必要があります。山形新幹線米沢トンネル(仮称)整備の早期事業化に向け、様々な機会を捉え、政府や関係機関への働きかけを強めてまいります。さらに、旺盛なインバウンド需要を最大限に取り込むため、空港の滑走路延長を含めた機能強化について検討してまいります。
また、日々の暮らしの安心のために、健康づくりや予防医療の充実、医療的ケア児や発達障がい児への支援体制の整備、超高齢社会を見据えた持続可能な医療・福祉提供体制の確保等を進めてまいります。
さらに、地域交通や医療、防災など様々な分野においてデジタル技術により地域課題を解決し、利便性の向上につなげてまいります。
3つ目は、「誰もがいきいきと働ける山形県」であります。
県民総活躍で新たなイノベーションを生み出し、「産業の稼ぐ力」を向上させていくため、常に新たな挑戦を続けていかなければなりません。
本県の強みであるものづくり産業のさらなる発展に向けて、県民所得の向上を意識し、DX・GXなどの新たな技術や国内外の活力の取込みに努めながら付加価値の向上を図るとともに、大学、産業界等とも連携し、即戦力人材の育成を進めてまいります。
さらに、高度外国人材やプロフェッショナル人材など、国内外の人材の受入れ・活躍を促進してまいります。また、女性非正規雇用労働者の正社員化や賃上げの支援に引き続き取り組むとともに、ワーク・ライフ・バランスの確保やテレワークの導入、リスキリングの推進等、多様な人材が活躍できる環境づくりにも力を注いでまいります。
加えて、起業・スタートアップや事業承継など、新たなビジネスの創出や次世代への円滑な承継についても、しっかりと支援してまいります。
本県の基盤産業である農林水産業の持続的発展に向けても、引き続き、力を入れてまいります。スマート農業のさらなる推進やデジタルツールを活用した販路開拓等により経営環境を高めるとともに、多様な担い手の確保を進めてまいります。
また、農林水産業は観光業や食品加工業などにも波及する、裾野の広い産業であります。県産農林水産物のブランド力の強化や「やまがたフルーツ150周年」を契機とした県産フルーツ全体の認知度向上を図り、交流人口の拡大にもつなげてまいります。
4つ目は、「関係人口と交流人口の拡大による元気な山形県」であります。
人口減少下にありましても、本県が持続的に発展していくためには、観光・交流の拡大により国内外の活力を呼び込むほか、あらゆる手段を用いて関係人口を拡大し、本県のファンや応援団を増やしていくことが重要であります。
出羽三山に代表される精神文化や四季折々に表情を変える豊かな自然、高品質な美食・美酒など、本県ならではの地域資源を活用した多様で価値の高い体験型観光コンテンツの充実を図るとともに、航空・鉄道等の高速ネットワークから県内周遊や近隣県との移動を支える二次交通まで、交通の機能強化や利便性向上を目指してまいります。
併せまして、関係機関や近隣県などとも連携を図りながら、これまで築き上げてきた人的ネットワークやデジタル技術なども活用して、県産品の販路拡大や輸出の拡大を進めてまいります。
これらの取組みにより、本県の魅力を国内外に発信することで多くの人々とつながり、さらに関係を深めていくとともに、多様な交流を通して、将来的な移住・定住にも結び付けてまいります。
5つ目は、「県民一人ひとりが輝く山形県」であります。
県民一人ひとりが家庭や職場、地域の中でその力を思う存分に発揮していただくためには、包摂性・寛容性の高い地域をつくっていくことが重要であります。とりわけ、人口減少が進む中にあって、より一層、外国人材を受け入れ、定着を促していくことが必要不可欠であります。
このため、留学生の受入れや外国人材の県内企業での就労を促進してまいります。併せまして、暮らしに関する相談体制の強化や日本語学習環境の充実など、外国人も安心して暮らせる環境整備や日本人と外国人の相互理解の促進と交流機会の拡大を図り、地域を構成する一員として、ともに活躍できる多文化共生社会の構築を進めてまいります。
また、若者や女性も住みやすい地域づくりに向けて、自由度の高い働き方の拡大など就業環境の整備や、地域・企業等におけるアンコンシャス・バイアスの解消などを促進してまいります。
加えて、高齢者や障がい者もその能力を発揮し意欲に応じた就労や社会参加を拡大するなど、県民の皆様の多様な活躍を後押ししてまいります。
現在、第4次山形県総合発展計画の後期実施計画について策定作業を進めております。新たな行財政改革推進プランや、各分野の個別計画である山形県産業振興ビジョン、農林水産業元気創造戦略、山形県教育振興計画などにつきましても、今年度末の終期に合わせ、新たな計画の策定を進めているところです。
これらにつきましては、今後、県議会をはじめ、県民の皆様、市町村の御意見をお聞きしながら検討を進め、3月末までに決定してまいります。来年度以降は、これらの新たな計画を中心に具体的な施策や取組みを推進してまいります。
決意・結び
私は、これまでも、県民の生命と生活を守ることを最優先に、活力あふれる山形県の実現に取り組んでまいりました。
今後も、県民の皆様や市町村としっかりと対話を重ね、現場の声を大切にしながら、総合発展計画の基本目標である「人と自然がいきいきと調和し、真の豊かさと幸せを実感できる山形」の実現に向けて、全力で挑戦してまいります。
次に、このたび提案いたしました令和7年度当初予算案を御説明申し上げます。
令和7年度当初予算を取り巻く環境
令和7年度の政府の地方財政計画につきましては、社会保障関係経費の増加や物価高が見込まれる中、地方が様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方一般財源総額について、令和6年度を上回る額が確保されました。
一方で、本県の一般財源につきましては、県税、地方交付税はいずれも前年度を上回るものの、社会保障関係経費や公債費が引き続き高い水準で推移するなど、厳しい予算編成を余儀なくされたところであります。
他方で、本県を取り巻く情勢は、人口減少の加速、自然災害の頻発・激甚化、物価高騰の長期化など課題が山積しております。
このたびの当初予算案は、こうした直面する課題に対応しながら、将来を見据え、県民の安全・安心の確保に向けた取組みを強化し、県民の皆様とともに山形県の明るい未来を創っていくため、「やまがた"みらい共創"予算」として、編成したところであります。
令和7年度主要施策
それでは、新年度における主要施策の概要について、「令和7年度県政運営の基本的考え方」に掲げる3つの施策展開の方向性に沿って、御説明申し上げます。
はじめに、「中長期を見据えた『人口減少対策』の強化」について申し上げます。
若年層、特に女性の県外流出が続く状況を打破していくためには、多くの人々を惹きつける、魅力あふれる山形県をつくっていくことが重要であります。
そのためにも、こどもや女性、若者、高齢者など、多くの方々の県政に対する考えや望む施策について、より緊密な対話を通して県政に反映させていくことが、これからの県づくりにあたって大切な視点であると考えております。
このため、県民の皆様の声を直接お聞きする場として、新たに「『県民まんなか』みらい共創カフェ」を開催し、頂戴した御意見等を県政に活かしてまいります。
子育て世代への支援としましては、安心してこどもを生み、育てることができるよう、0歳から2歳児の保育料無償化に向けた段階的な負担軽減の取組みを拡充します。令和3年度から市町村とともに子育て費用の負担軽減に取り組んできたところですが、このたび対象世帯を拡充することといたします。
若者・子育て世帯への移住支援金につきましては、若者世帯でも2人以上の世帯であれば20万円に、子育て世帯も20万円に拡充いたします。これにより、若者かつ子育て世帯の場合、40万円の給付が受けられることとなります。このように、本県独自の移住支援金を拡充し、移住者の増加に向けた取組みを推進してまいります。
学校教育環境の充実としましては、新たに、県立産業系高校等の生徒を対象とした外国人講師とのマンツーマンのオンライン英会話や、地元企業の外国人材や留学生との対面交流に取り組んでまいります。また、起業家精神の育成に向けて、「やまがたイノベーティブマインドスクール(仮称)」を開校し、地元企業や大学等による伴走支援を実施してまいります。
これらの取組みを進め、次代の山形を担い地域を支える人材の育成・確保に努めてまいります。
さらに、東北では初めての取組みとなりますが、フリースクール等を利用する経済的な困難を抱える世帯を対象に、利用料の一部を支援する取組みを開始し、多様な教育機会の確保につなげてまいります。
暮らしやすく、活力あふれるまちづくりを進めていくために、まず、若者・女性の山形での多様な働き方や暮らし方、活躍する姿の県内外への発信を通して、県内定着・回帰を促進してまいります。併せまして、アンコンシャス・バイアスの解消に向けた啓発や、性の多様性に関する理解促進などに取り組み、誰もが個人として尊重され活躍できる包摂性・寛容性の高い地域づくりを進めてまいります。
さらに、地域において外国人住民も安心して暮らせる環境整備など、事業者や市町村等が自らの創意工夫により行う取組みを支援するとともに、多文化共生に対する理解を深めるための交流イベントの開催等を通して、国籍に関わらず、誰もが地域を構成する一員として、ともに活躍できる多文化共生社会の構築を進めてまいります。
加えて、屋内スケート施設を含む新スポーツ施設につきましては、今年度の有識者会議で議論を進めている内容を踏まえ、来年度、さらに検討を深めてまいります。また、県立博物館の移転整備に向けましては、来年度末までの基本構想の策定を目指し、その取組みを進めてまいります。
県民生活の基盤であり、国内外の活力を呼び込むためにも重要である交通ネットワークの形成につきましては、山形新幹線米沢トンネル(仮称)の整備に備え、引き続き5億円を山形新幹線新トンネル整備基金に積み立てるとともに、山形新幹線新トンネルの整備効果を高めるため、沿線の活性化や利用拡大に向けた取組みを県内全域で強力に展開してまいります。
また、国際チャーター便の受入拡大に向けて、庄内空港の機能強化を図るため、ターミナルビルの国際線施設の整備について、関係機関との調整等を行ってまいります。併せまして、山形・庄内両空港に係る空港将来ビジョンの策定に向け、滑走路延長等も含め、空港の将来的な在り方について検討してまいります。
次に、「時代の変化を推進力とした『産業の稼ぐ力の向上』」について申し上げます。
県内中小企業・小規模事業者の経営力強化のため、新技術・新サービスの開発支援をはじめ、収益力の向上やDXの推進、災害時の事業継続に向けた設備投資などを支援してまいります。
また、令和8年度に米沢商工会議所新会館内に設置を予定しているイノベーション連携拠点の本格稼働を見据え、県、米沢市、米沢商工会議所及び山形大学工学部の4者で連携し、地域におけるイノベーション創出の仕組みづくりにも取り組んでまいります。
環境と経済の好循環の創出に向け、県内企業による「脱炭素経営」を推進することにより、市場での競争優位性の維持・確保を図るとともに、GX関連産業への参入支援を行ってまいります。
蔵王の樹氷復活に向けては、林野庁の調査研究などで得られた知見をもとに、オオシラビソ林の再生計画を策定し、再生を加速させてまいります。
併せまして、「やまがた百名山」でのデジタルスタンプラリーの開催など、山形県の魅力そのものである「山」のさらなる魅力向上・発信による利用拡大や、登山者と山岳関係団体との交流による環境保全活動などの取組みを通して、環境資産を活かした産業振興・交流拡大も進めてまいります。
明治8年、本県に「さくらんぼ」をはじめとする果樹の苗木が導入され、今年はそれから150年目の記念すべき節目の年、「やまがたフルーツ150周年」を迎えます。
6月に「さくらんぼメモリアルフェスタ」、8月に「やまがたフルーツEXPO」を開催するとともに、県内外における各種媒体を活用したPRを通して、本県フルーツのさらなる魅力発信と果樹産地の活性化につなげてまいります。
また、気候変動に強く、生産性の高いさくらんぼ産地づくりに向け、高温対策技術の導入支援や、スマート農業を活用した未来型果樹栽培を推進してまいります。
さらに、デジタル技術を活用し、生産者と地域のレストランやホテル等の事業者をつなぐことにより、通常の流通では扱いにくい地域食材の販路開拓を図るなど、農林水産業の経営環境を高めてまいります。
国内外からの観光・交流人口の拡大に向け、観光客のニーズが多様化する中、年齢、障がいの有無や国籍等に関わらず、旅行者の誰もが、山形での観光を「安全」かつ「快適」に楽しむことができるよう、「アクセシブルツーリズム」を推進し、「機運醸成・情報発信」や「受入態勢の整備」を行ってまいります。
また、インバウンド需要が活況を呈する中、多くの外国人観光客が銀山温泉を訪れています。この観光需要を県内他地域にも波及させていくため、銀山温泉と県内観光地を結ぶ広域連携に向けた取組みを進めてまいります。
最後に、「様々なリスクへの対応強化による『安全・安心の確保』」について申し上げます。
令和6年7月の大雨災害は、本県における自然災害としては過去最大の被害額となりました。被災した施設等の復旧・復興を着実に進めるとともに、市町村と連携し、被災者の皆様に対する支援も引き続き切れ目なく行ってまいります。
災害が頻発・激甚化する中にあって、防災・減災対策が喫緊の課題であります。このため、地域防災力の強化・向上に向けた有識者会議を設置し、本県における防災対策の今後の方向性について検討してまいります。
災害に強い強靭な県土づくりとしましては、豪雨災害を踏まえた治水対策の推進を図るとともに、土砂災害が発生するおそれのある箇所の「警戒区域」の指定に向けた基礎調査を実施するほか、河川堤防の点検や予防修繕の充実に加え、地震から命を守るため住宅の改修や減災対策への支援を行ってまいります。
女性防災士の増加に向けて、県内4地域において、新たに「女性防災士育成セミナー」を開催するほか、本県の防災学習に係るアクションプランを策定し、実効性のある防災教育施策の検討・展開により、自助・共助の強化に向けた県民の防災意識を高め、地域防災力の向上につなげてまいります。
県や市町村の災害対応力の強化につきましては、警察官の災害警備活動の高度化に向け、レスキューボートやウェットスーツなど災害警備活動用資機材の充実を図るとともに、SUV型の警察車両を整備してまいります。
また、災害時を想定した新たなオンライン診療モデル事業に取り組むとともに、災害発生時の迅速な避難、円滑な避難所運営に向けた防災アプリを導入してまいります。
日々の暮らしの安心の確保に向け、医療提供体制の充実につきましては、これまで、県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編に係る検討を重ねてまいりましたが、今年度中に新病院整備の基本構想を策定し、来年度には基本計画の策定に取り組んでまいります。
また、ひとり親家庭が自立して安定した生活を送ることができるよう、様々な相談対応や生活向上のための支援を行うとともに、低所得のひとり親世帯への県産米提供や、就職に有利な資格取得に向けた支援などを行ってまいります。
さらに、こども食堂につきましては、これまでの運営に対する支援に加え、来年度からは立上げに対しても新たに支援を行い、より一層、こどもが安全に、安心して過ごせる居場所づくりに取り組んでまいります。
加えて、社会環境の変化やコロナ禍を経て、人と人とのつながりが希薄化し、孤独・孤立の問題が顕在化・深刻化しております。官民連携プラットフォームの設置や専用ポータルサイトの開設など、孤独・孤立を予防する地域づくりを推進してまいります。
イノシシ・クマなど野生鳥獣による生活被害や農林水産被害が発生する中、市町村や大学、猟友会と連携し、持続可能な被害防止体制の構築についての検討や、新たな手法によるモニタリングの実施、防除体制強化への支援など、鳥獣被害防止対策をより一層、推進してまいります。
これら施策を推進するため所要の予算を計上した結果、一般会計当初予算案の総額は、6,754億1,900万円となりました。
また、公債管理特別会計など10特別会計予算案は、合計で2,637億7,879万円余となりました。
財政運営について、今後を展望いたしますと、依然として多額の財源不足が生じる厳しい状況が見込まれることから、産業振興を通して、県民所得の向上、県内経済の成長につながる好循環を生み出し、県税収入の増加を図っていくことが極めて重要であると考えております。
そのうえで、今回の予算編成と同時に策定した「山形県財政の中期展望」におきまして、歳入面では、県有財産の売却や有効活用の促進、基金や特別会計の利用見込みのない資金の活用等を図り、歳出面では、事務事業の見直し・改善や、行政経費の節減・効率化など、歳出の見直しを今まで以上に徹底して取り組むこととしております。
こうした歳入・歳出両面からの対策を講じつつ、中長期的な財政健全化を推進するため、実質的な県債残高の減少と調整基金の確保に引き続き努めてまいります。
令和6年度2月補正予算
次に、令和6年度2月補正予算案について御説明申し上げます。
物価高騰の影響を受ける生活者・事業者への支援につきましては、物価高やエネルギー価格の上昇が引き続き大きな影響を及ぼす中、これを乗り越え、県民生活の安全・安心や県内経済の持続的成長につなげていくため、物価高騰への対応を力強く展開するものです。
まず、生活者への支援としましては、生活困窮者等に対して食料品等を提供するフードバンク活動への支援や、県内事業者からの購入で特典が受けられる省エネ家電買換えキャンペーンの実施、県立学校給食の食材購入費支援等を行ってまいります。
事業者への支援としましては、物価高騰により厳しい経営状況にある医療・福祉施設や地域交通、中小企業者、農林水産業者等へ支援してまいります。これに加え、モーダルシフトや物流の効率化に資する取組みへの支援を行うほか、県内中小企業・小規模事業者の収益力の向上や持続的な発展を図るため、「中小企業まるっとサポート補助金」を、令和7年度当初予算から一部前倒しして実施いたします。
防災・減災、国土強靱化の推進のための公共事業等につきましては、内示状況や事業費の精査等を踏まえ追加・整理いたします。
災害・諸課題への対応につきましては、災害への備えとして、避難所生活における環境改善等に向け、テント式パーティションなどの資機材を整備するほか、介護施設及び障がい福祉施設職員の処遇改善に係る経費への支援などを行ってまいります。
また、今冬の降雪状況や執行状況を踏まえ、道路除雪費を増額するほか、県立病院の厳しい経営状況を踏まえ、一般会計からの負担金を増額いたします。
こうした対応に、今年度の執行実績等に伴う補正を合わせますと、一般会計の2月補正予算案の総額は、373億100万円の減額となりました。
繰越明許費につきましては、総額で127億7,183万円余を増額補正いたします。
予算以外の案件
次に、予算以外の案件の主なものについて御説明申し上げます。
山形県子育て基本条例の一部を改正する条例の制定につきましては、こども基本法の趣旨や近年の多様化・複雑化するこども・子育てを取り巻く社会環境を受けて、こどもの意見の尊重に関する規定やこどもへの虐待等の防止に関する規定を設けるなど、こどもの健やかな成長に向けた取組みを推進するためのものであります。
山形海区漁業調整委員会委員の任命につきましては、委員の任期満了に伴い、提案の者を適任と認め、御同意をお願いするものであります。
以上が、今回提案いたしました議案の概要でありますが、内容の詳細につきましては、議事の進行に従いまして、関係部課長より御説明申し上げますので、よろしく御審議のうえ、御可決くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ