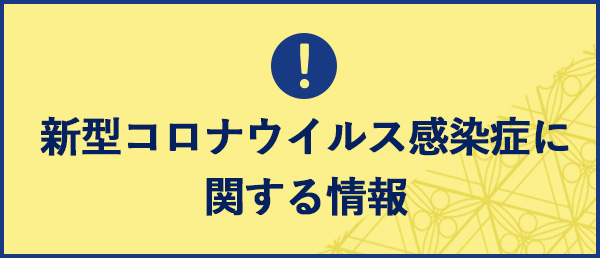ホーム > 県政情報 > 知事室 > 知事メッセージ > 談話・コメント・訓示 > 談話・コメント・訓示 2025年 > 令和7年度当初にあたっての職員に対する知事あいさつ
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
令和7年度当初にあたっての職員に対する知事あいさつ
令和7年4月1日
職員の皆さん、おはようございます。
大雪のシーズンが終り、寒暖を繰り返しつつも、ふきのとうや福寿草、ヒヤシンスなどが花開き、ようやく春の訪れを感じる季節となりました。
本日から、いよいよ令和7年度のスタートです。
さて、本県の人口は、直近で自然減8割、社会減2割の割合で減少が加速しており、今年中に100万人を割ることが見込まれております。
調べてみましたら、大正14年に100万人を超え、昭和25年にピークの135万7千人超となり、以来少しずつ減少してきているということがわかりました。
つまり、大正14年以前は人口が100万人以下だったということです。そして、大正14年以降100年ほどは人口100万人以上が続いているということであり、まもなく人口が100万人を割るということは現代を生きる私たちにとって大変ショッキングに感じられますが、歴史的に考えれば、一つの通過点なのであって、危機感を持ちつつも、決してマイナス思考に陥らないことが大切であります。
もちろん、人口は全ての尺度となり得るものであり、県の活力の源であるといえます。
故に、先般策定した第4次山形県総合発展計画の「後期実施計画」におきましても、人口減少対策を最重要課題と位置づけ、減少のスピードの緩和に取り組む「抑制策」と、減少が進む中にあっても生活の質と地域活力の維持向上を図る「対応策」の両面から、取り組むこととしております。
大事なことは、こうした状況にあるからこそ、決して後ろ向きにならず、きちんと前を向いて、本県の強みを最大限に活かすとともに、新しい強みを創造していくことが大切であり、その気概が求められていると思います。
また、災害の頻発化・激甚化や長引く物価高騰などを踏まえ、県民の安全・安心の確保に向けた取組みをなお一層強化するとともに、社会経済情勢の変化をチャンスと捉え、デジタルの活用による生産性向上や利便性向上、GX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進、そして観光交流などで国内外の活力を摂り込むことや外国人材の活用など、時代の変化に柔軟に対応し、新たな取組みにも積極的にチャレンジしていくことが重要であります。
こうした、未来につながる持続可能な県づくりに当たっては、「令和7年度 県政運営の基本的考え方」で示したとおり、
1 中長期を見据えた「人口減少対策の強化」
2 時代の変化を推進力とした「産業の稼ぐ力の向上」
3 様々なリスクへの対応強化による「安全・安心の確保」
これら3つを施策展開の主な方向性とし、これまでの取組みを着実かつ継続的に推進するとともに、直面する新たな課題にも積極果敢にチャレンジしていきましょう。
そもそも県政は、「県民の幸せ」と「県勢の発展」を目指してなされるものでありますが、このことは人口の増減にかかわらず、不変のものであります。
むしろ、人口減少の時代だからこそ、なお一層県民のウェルビーイングを実現し、県民が前を向いて、未来に明るい展望を抱くことができる山形県を県民とともに創っていくことが肝要であると思います。こうした考え方のもと、今年度、みらい企画創造部に「いきいき山形未来企画室」を新設し、「いきいき山形未来企画監(兼)次長」を配置いたしました。
また、米沢トンネル(仮称)の整備や米坂線の復旧、山形・庄内空港の更なる利用拡大など、本県交通網の機能強化に向けた重要施策を強力に前に進めるため、「交通機能強化・DX推進監(兼)次長」を配置いたしました。
さらに、頻発化・激甚化する災害等の教訓・課題等を踏まえ、地域防災力の更なる充実・強化を図るため、防災危機管理課に「防災学習・防災DX推進室」を新設いたしました。
こうした新しい体制のもと、「県民の幸せ」と「県勢の発展」を目指し、全力で取り組んでいきましょう。
ここで、今年度の本県における大きな動きやトピックに触れたいと思います。
今年度は、本県でさくらんぼや西洋梨などの栽培が始まってから150年の節目を迎えます。先人たちが「いちずにかじつ」に取り組み、挑戦を続けてきてくれたからこそ、現在の「さくらんぼ県やまがた」があります。
さくらんぼをはじめとする本県の果樹産業にとって記念すべき年でありますので、県全体で「やまがたフルーツ150周年」を盛り上げ、県産フルーツの魅力発信や果樹産地の活性化、さらには、関係人口や交流人口の拡大にもつながるよう、部局横断で積極的に取り組んでいきましょう。
また、東北公益文科大学ついては、昨年8月に県と庄内2市3町、学校法人東北公益文科大学の間で公立化及び機能強化に向けた基本合意がなされました。社会や地域を取り巻く環境が変化する中、より魅力的で特色ある大学として、地域に必要とされる人材を育成し輩出するため、関係市町や大学等と連携し、来年令和8年4月の公立化を目指して、しっかりと準備を進めていきましょう。
そして、人口減少による国内・県内の観光需要の縮小が見込まれる中、旺盛なインバウンド需要を本県に広く取り込み、交流人口を拡大し、地域経済活性化につなげていくことが重要であります。昨年9月に本県全域が高付加価値旅行者への誘客を目的とした観光庁のモデル観光地に選定されたことも大きな追い風になると思います。また、インバウンドだけでなく、アウトバンドもあわせた双方向の交流が持続的な発展には欠かせませんので、イン・アウト両方の視点を持って、観光施策に力を入れて取り組んでいきましょう。
さらに、西村山地域における医療提供体制については、県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編に向けて検討を重ね、昨年度、基本構想を策定いたしました。今年度は、建設予定地や新病院の機能などを定める基本計画の検討に取り組み、令和13年度の開院を目指して、引き続き、準備を進めていきましょう。
ここまで、今年度の大きなトピックについてお話ししてきました。
最後に、防災力の強化・向上について申し上げます。
昨年7月の豪雨災害は、本県における自然災害としては過去最大の被害となりました。職員の皆さんには、被災市町村をはじめ、政府や関係機関と連携し、迅速な災害対応や応急復旧に取り組んでいただきましたし、現在も被災者の生活再建、道路、河川、農地等の本格的な復旧・復興に力を注いでいただいており、改めて感謝を申し上げます。
今般の豪雨災害や能登半島地震では、関係者間の情報共有や広域的な応援体制の構築、避難所の快適な生活環境の確保など、災害対応における様々な課題が浮き彫りなりました。
人口減少が進む中で激甚化・頻発化している自然災害に対応していくためには、これまで以上に政府や自治体、関係機関等との更なる連携強化が必要であります。県民が安心して生活できるよう、より一層力を入れて防災対策に取り組み、災害に強い県づくりを進めてまいりましょう。
結びになりますが、職員の皆さんのウェルビーイングも非常に大切です。ウェルビーイングとは、心身ともに満たされた状態または「よい状態」を指す言葉であり、身体的・精神的・社会的の全てが満たされた状態のことをいいます。平たく言えば、「幸せな状態」、「充実した状態」などと言い換えられるようであります。
まず、身体を良くするには食事と睡眠が大切であります。
食事は栄養バランスを考えて摂りましょう。たとえば、県庁食堂の弁当や定食などは、肉や魚はもちろん野菜も摂ることができて体に良いと思います。安くて簡単な食べ物に目が向きがちかもしれませんが、若い時から健康に気を配るようにしてこそ、中高年になっても健康体でいられるものです。皆さん自身の将来への投資と考え、しっかりと栄養を摂りましょう。
次は精神、心ですね。
心は、目に見えないものですから、主観的にならざるを得ません。
一人一人にそれぞれの幸せや良い状態があるかと思います。
時間ができた時、皆さんの「良い状態」とは何か、「幸せ」とは何かを考えてください。といっても、あまり難しく考えず、どんな時が楽しいか、嬉しく感じるか、ゆっくりできるかといったことだと思うのです。
家族と一緒の時だったり、趣味のスポーツや畑仕事だったり、旅行や温泉、買い物や飲み会、友人とのおしゃべりだったり、散歩や森林浴、読書、映画鑑賞などもあるでしょう。小さな絵を飾るだけで心が和んだりします。様々あると思いますが、皆さんの心の状態を良い方向に持っていけるようなことを実践していただきたい。
それが心の栄養となり、健全な精神へとつながり、明日の活力へとつながっていくのだと思います。
時には立ち止まって、皆さん自身の心を見つめ、心の栄養を補給するよう努めてください。
以上のように、皆さん自身のウェルビーイングも大切にしながら、日々の仕事を行うに当たっては、「県民視点」、「現場主義」、「対話重視」、この3つの姿勢を改めて大切にしていただき、新しいことに積極果敢にチャレンジしていただきたいと思っています。
令和7年度も「県民のための県政」、「県民のための県庁」であることを深く心に刻み、県民の皆さんが、ここ山形県に暮らして良かったと幸せを感じる山形県づくりに、共に汗を流していきましょう。
今年度もよろしくお願いいたします。
お問い合わせ