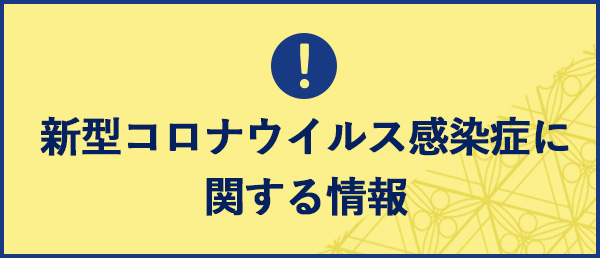ホーム > アレチウリ
更新日:2025年3月28日
ここから本文です。
特定外来生物アレチウリについて
外来生物法により特定外来生物に指定され、原則、栽培や生きたままでの運搬などが禁止されています。
 |
1特徴
北アメリカ原産の一年生のツル性植物です。長いもので10メートル以上に生育します。
輸入大豆に混入した種子によって移入したものと言われています。
| 4月から10月 | 8月から10月 | 9月 | |
| 芽生え | 生長 | 開花 | 結実 |
 |
 |
 |
 |
|
同じウリ科のキュウリなどに似た双葉で芽生えます。 大きさは5cmから10cm程度になり、五角形の本葉をつけます。 芽生えの期間は、長い期間にわたり続きます。 |
生長するとハートのような形をした五角形の大きな葉が、白い毛の生えたツルから1枚ずつ生え、巻きひげを伸ばしながら他の植物に巻きつき、覆いかぶさりながら繁茂します。 |
白色の直径1cm程度の雄花と直径6mmほどの雌花 |
硬いトゲがあり、素手で触るとけがの原因になります。 |
クズとの見分けかた
アレチウリはクズと似ています。クズも生態系被害を及ぼしますが、特定外来生物ではないため、移動の禁止などの法的制限はありません。
違い
花の色(クズ:紫、アレチウリ:白)、葉の付き方(クズ:茎1本につき3枚の葉、アレチウリ:茎1本に1枚の葉)
 |
2生息環境
農地や河川敷、道路のり面などに生育します。
 |
 |
3影響
植物に絡みつき、覆ってしまいます。覆われた植物は、日光を遮られて枯れてしまいます。
土壌に種を蓄積するので、大豆畑に侵入し、繁茂するとその畑では大豆が作れなくなる被害も報告されています。
4県内での侵入状況
環境省では、平成5年度より「特定外来生物の市町村別侵入状況把握のためのアンケート調査」を実施、その結果を国立研究開発法人国立環境研究所の侵入生物データベースに反映させています。
この調査は、都道府県を経由して市町村からもデータを集めますので、もしまだ侵入が報告されていないところで見つけた場合は、市町村の担当課まで御連絡ください。(ご自分の所有地及び管理地であれば駆除も実施してください。)
侵入生物データベース(国立研究開発法人国立環境研究所)(外部サイトへリンク)
5駆除方法
方法
(侵入初期に推奨)手で抜き取る
侵入初期であれば簡単にできますが、いったん蔓延すると現実的な方法ではありません。
(推奨)カマや機械による刈り取り
一年生のため、地上部の刈り取りでも効果はあります。面積が広い場合は有効な方法です。
芽生えが続くので複数回必要です。
(場所によっては推奨)除草剤使用
他の植物を枯らしてしまったり、薬剤が周辺環境へ飛散して悪影響を及ぼす恐れがありますが、大豆圃場では有効なやり方も研究されていますので、各総合支庁の農業技術普及課までお問い合わせください。
ポイント
どうやって?
アレチウリは、「種子」「生きたままの全草」の移動が禁止されています。「種子」は枯れないので移動ができません。
「種子のない全草」を抜いた後はゴミ等に入れて密閉し、枯らしてから「燃えるゴミ」に出してください。
いつ?
最大で10mにもなるため、生長すればするほど労力がかかります。芽生え直後の駆除が最も抜きやすく、効果的です。
どれくらいの頻度で?
5月から10月まで芽生えが続きますので、こまめに駆除することが重要です。種がつく前の駆除をお願いします。
いつまで?
土壌に種を蓄積する可能性があるので発芽が見られなくなるまで、長期的に継続的な活動が必要です。
お問い合わせ